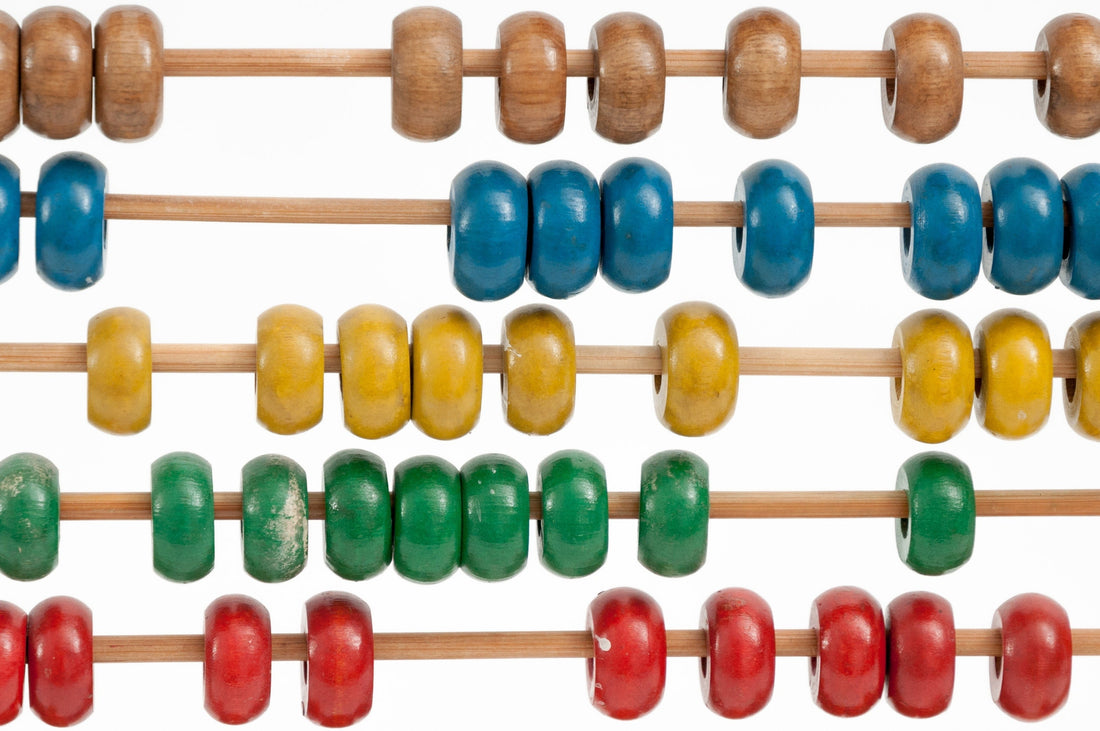Journal
過去の財産
企画担当のRです。先日、事務所にある商品サンプルを整理をしました。一応、置き場所を決めて管理しているのですが、打ち合わせで使用したり、取引先に貸し出したり、営業で持ち出すこともあったりで、すぐバラバラになりがちなサンプルたち。一度整理しよう、ということで年度別にこれからも置いておきたいもの、必要ないものなど分類していきました。大量のポロシャツたちや、売れているC78W(ミリタリーカーゴ)の後ろゴム仕様など商品化に至らなかったサンプルたちもた~くさん出てきました。今見ると「お、これイイね!」というものも。その中には、売り切れてしまった初代『RUSH(ラッシュ)』も発見! 唯一のイエローラベルを見て、 「なつかしい~~!!」と叫んでしまいました。まだ4年目のブランドですが、過去を振り返るとこんなにいろいろ商品作ってたんだなぁ、としみじみしちゃいますね。商品化したものも、ボツになってしまったものも、すべて大事な財産。 何年かして商品化されることだってあるかもしれません。・・・というわけで、 商談スペースの棚もスッキリ!展示会を控えている20SSの商品も並べることができそうです。では、よい週末を~!☆初代は売り切れてしまいましたが、便利なスマホポケット付き『RUSH』はデザインや素材を変えて引き継がれています!・初代より伸びる生地に変更! RUSH 2nd!・後ろウエストゴム仕様!らくちんなRUSH EASY!・クラウドファンディングでも大好評をいただきました チノパンRUSH。
目標金額達成しました!!
企画担当Cです。 先日Rのブログでお伝えした、クラウドファンディング第3弾!【満員電車対応3Dボディーバッグ】 https://www.bmc-tokyo.com/blogs/products/products-118 8/14に開始7日で目標金額を達成致しました! ご支援頂いた皆様、本当にありがとうございます! 現在、達成率109%! 引き続き、応援頂けると幸いです! まだページをご覧になっていない方は、コチラからご覧いただけます。 おススメは超々お得な2個セット(^^♪ 男女関係なく持てるデザインなので、ご家族や恋人とお揃いで持てますよー。 是非皆様、ページを覘いてみてくださいね!!
【スマホ生活を最適化するチノパン】発送しました!!
企画担当Cです。 クラウドファンディングで皆様にご支援を頂いた【スマホ生活を最適化するチノパン】を本日発送しました!! 4月5日からクラウドファンディング募集が始まり、終了したのが5月19日。 この3か月、進捗状況をお伝えしてきましたが、 https://www.bmc-tokyo.com/blogs/products/products-117 いよいよの発送とたくさんの梱包を目にして、感無量です! ご支援頂いた皆様、本当にありがとうございました!! ロールアップしても決まるテーパードシルエットなので、裾上げ無しでもすぐ着用頂けます(=^x^=) 到着を楽しみにしていてくださいね!!
アパレルの在庫廃棄は悪ではない!余らせたくなければ”適品”の精度を上げよ - 勘性とそろばんのバランス(後編)
ブリッツワークス代表、青野氏と佐藤マサさんの対談後編です。 前編はこちら https://www.bmc-tokyo.com/blogs/journal/journal-73 アパレルの在庫問題を解決するのはMDの精度? - 勘性とそろばんのバランス(前編) Q. どうしたら佐藤さんのように人にうまく教える事ができますか? 青野:自分の中で腹落ちしてないと人に教えれないですもんね。 佐藤:一番勉強になってるのは学生に教えてることですね。彼らのような若者に興味持ってもらうためには、どんな喋り方をしたらいいのか?どんな切り口で話せばいいのか?ってことを考えるんです。そうやって学生に受けたものを、今度はブランドで話すとすごくわかってもらえるんですよ。自分が勉強させられる場ですよ本当。 アパレルは社会に出てからの教育が整備されてないですよね。アホな経営者は「教えたら人は辞める」って言う。けど、僕の講義受ける人は若い人ばかりです。仮に辞めたとしても教育受けてるんだから、その人自体は育ってるんですよ。 これって簡単な計算なんですが、例えば僕の講義受けるのに30万かかるとしましょう。で、粗利率が50%のアパレルだったら、講義のおかげで年間で60万円売上伸びたらペイするんですよ。即戦力で社員取ってくるって1000万プレイヤー取ってきたら2000万円の売上作らなきゃいけない。そっちの方がハードル高い。 青野:うちも今、ECサイトの見積もり出していて、見積もりが数十万円なんですが、これを回収するにはいくら売上作らないといけないか、それが半年なのか、一年なのか、を前始末するって事ですよね。これをやる人たちが本当に少ないと思います。MDやってる人でも100分率わかってなかったりしますからね…。 佐藤:そう、そうなんですよ。でもそれをバカにしないでちゃんとわかりやすく教えないといけない。どれだけわかりやすく噛み砕いて教えてあげれるかが僕の仕事ですから。 青野:マサさんにオファーする企業は何を求めてるんですか?数字がいかに重要かを社員に理解させたいからオファーをするんですか? 佐藤:社員が数字に強い企業だからってオファーが無い訳ではないんです。企業として、指標がよくわからなくなってるから整理してほしいんだろうし、もっと簡単にしたいんですよ。 企業の分析ってザルなのは知ってるから、そこで役に立てるかなって思ってました。だからブログなんかでも愚直に同じ事発信し続けてます。そんな中でも、社長からダイレクトにくる仕事はうまくいくし、人を介するとうまくいかないですね(笑) あと、なるべく相手の求めるものに寄り添う努力はしますよ。それは言葉でも。Webの人なら「セッション」とか「コンバージョン(CV)」とか。CVは別の企業だったら「決定率」とか「買い上げ率」だったりします。それを最初に確認しますね。相手の実務者に役に立たないと僕の仕事は意味ないですから。そこはめっちゃ意識してますよ。 Q. どうしたらアパレル業界の経営は改善されますか? 佐藤:企業の問題点を見抜くには、やるべき事は決まってるんです。基礎を徹底的に磨く。物事の本質を考える。現場に行く。顧客の近くにいる。って事です。 余談ですけど、僕は企業のキャッシュフロー計算書がすごく好きで、それを自分に置き換えたりします。今から自分が仕事が無くなっても、どこまでは普通に生きていけるか、みたいな(笑)実生活でも前始末してるんですよ。これは過去の経験からですね。起業してから3年くらいはほとんど仕事なかったからシミュレーションばっかりしてました。預金通帳の残高が残り13000円になった時は死にたくなりましたよ(笑) あと現状、アパレルに入っているコンサルが機能していませんね。特に今の弊社の価格設定は、コンサル価格をぶっ壊したような基準なんですが、そのせいでアパレルのコンサルから目をつけられちゃってる。 更に仕事期間をできる限り短くしたりと、とにかく相手が喜ぶ事を常に考えてますし。あんまり儲かりませんけどね。でもアパレルのコンサルって、最後はもめて終わりのケース多いですからそれよりはいいかと(笑) 青野:もう経営者になったらいいんじゃないですか? 佐藤:実は将来的に小売の企業買おうと思ってるんですよ。自分は0を1にする能力は全く無いんですけど、1を10にするのは得意なんです。小売なら何でもよくて、街の商店街のタバコ屋でもいいと思ってるんですよ(笑) 青野:僕は逆に0を1にするのは得意なんですけど、1を10にするには自分の情熱が続く気がしないんですよ。 佐藤:過去、アパレル業界には創業の才能ある経営者は結構いたんですけど、業界をよくしてくれることはなかった。それは経営をしっかり学ばなかったから。みんなポルシェ乗り回して遊んでる場合じゃないですよ。一番の成功事例である柳井さんは創業者じゃないですしね。本当皆さん、良い経営者になる努力をしていないですね。 青野:だから僕はオーナー企業にしたくないんですよ。他社の資本も受け入れていいと思ってます。 佐藤:そういう青野さんのような創業者が生まれてこない限りはアパレルはよくならないでしょう。みんな良い経営者を目指して頑張ってほしいんです。これは自分が本当に創業の才能が無いからわかる事でもあります。 青野:苦労している人、よく考えてる人は言葉に真実味がありますよね。最近、高学歴の起業したい若者の話をよく聞いたりするんですが、D2C系ブランドと同じような、どこかで聞いた事ある話ばかりするんです。だから軽く感じてしまう。独立して初めて、リアルな数字をやっと知る事になるんでしょう。 実務で仮説を立てながら1シーズン回してみないとわからないのに、アパレルってソーシャルでフォロワー増えたら簡単に売れると思われてますよね。 佐藤:そういう人たちを見て思うのは、あなたたちのやりたい事で人はどう喜ぶの?って事。それが根本ですよ。自分の仕事でも、いつもこれは誰が喜ぶ?何のためにやってる?っていう根っこを考えてます。 自分ができる事で人が喜ぶ事ってなんだろうって考えた結果が今の業務に繋がってますからね。 青野:マサさんって、、、いい人ですね(笑) 佐藤:ありがとうございます(笑)基本的に最悪な事態想定しかしませんしね。 青野:それは共感しかないです。それにしても事前準備がすごいですね。僕は感覚派って見られがちなんですが、マサさんと同じで準備をすごく重視してるので共感できるところが本当に多い。 佐藤:とにかく後回しにしない事ですよね。だってどうやっても天才になれないんだから。イレギュラーに対応できないし、イレギュラーって絶対発生するから。 Q. アパレルの在庫問題についてどう思いますか? 青野:ロスを限りなくゼロにするために事前準備するじゃないですか。それってずっとうまくいってたんですか? 佐藤:自分でやる分にはね。でも今は教える側なので、人にやってもらわないといけないから、うまくいかない時もありますよ。解決策としては、徹底的に社長に動いてもらう。でも手遅れで在庫めっちゃ溜まってたりするんですよ。そういう時は廃棄するかどうかって話にもなりますね。 青野:いっぱい作ったら安くなるからって、無理に在庫積んだりしますからね。最近よく話題になる在庫の廃棄問題ってどう思います? 佐藤:捨てるのって全然悪くないと思ってますよ。ヴェトモンとか、捨てるのが悪だって発信してたりしますけど、本質的ではないですよね。物作ってる人たちはどうなるのって話になりますよ。しかも、実際に在庫問題がどうこうって言ってる会社ほど、そこの数字がザルだったりします。でもメディアが一番悪いですね。この本質をわからないまま報道してるから。 青野:うちも何万点て仕入れるんですけど、まだ捨てたりした事はないんですよ。何とか消化するような努力はしていて。それでも廃棄が叩かれてるって風潮はおかしいと感じてます。消化する努力はちゃんとしたのかって思ってしまいます。 佐藤:在庫廃棄を叩きだしたら物を作れなくなる。本当は5適の「適品」の精度上げるか、前始末して売る方法を先に考えておいたらいいだけなんです。生産の段階で生地ロットの問題もあるだろうけど、売れないなら生産するのは半分だっていいんです。その分のコストを生産した商品に乗せる方が健全ですよ。原価はあがっちゃうけど余らすよりいい。残ってセールして粗利削るんだったらその方が楽です。 ※5適…MDの基本要素の事。適品、適所、適量、適価、適時の5適。 青野:どこかの場面だけを切り取って、良いか悪いかって話にするから本質が見えなくなってますよね。 例えばうちのある商品を3000本生産する。その場合、恐らく6割しか消化しないってわかってるんですよ。だから本当は生産減らせばいいんですよ。でもその場合、原価は当然上がります。お客さんも高い商品は嫌だし、そうなると売価は上げれない。結果、うちが取れる粗利も減ってしまう。 でも僕は粗利って付加価値だと思ってますから、何故自分たちの付加価値を抑えてまで世の中に出さないといけないのかって考えてしまう。こうなると結局、最後の金額のつけを払ってるのはいつもメーカーなんですよ。 佐藤:国内アパレルの消費の10%はファーストリテイリングですよね。実は捨ててないのはユニクロで、服をいっぱい捨ててるのは他の会社。世界で見たら、ザラより捨ててるのはバーバリーですから。大量生産してないブランドが一番捨ててたりしますからね。 そういったブランドが商品を生産できるよう、物作りを支えてるのは誰なのかって話ですね。ゴミが大量に出ても日本の最新システムだったら全部燃やせますよ。やった事ない人間が綺麗事を言うなって思います。解決したいなら、みんなもっと数字を勉強したらいいんです。数字が解決策につながるんだから。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合理性やロジックを突き詰めながらも、ブランドや仕事に対する取り組み方は情熱的。まさに「勘性」と「そろばん」を絶妙のバランスで使い分けるマサさんの仕事力が言葉の節々から伝わってくるようなお話でした。 アパレルは今、国内外でも大きな過渡期にあり、その変化は過去、類を見ない程のスピードです。そんな世界で、対策を間違えない為には常に「疑う」事だとマサさんはしきりに言います。その気づきを与えてくれるものこそが数字なのだと。 用いるツールは数字という、一見無機質なものに見えがちですが、それを駆使しながら「人の役に立つ」事を常に考えるマサさんは、人一倍業界に対する愛情を持った人なのだと対話を通して感じ取られました。いかにわかりやすく、いかに再現性が高いか。そういったレクチャーによる後進の育成こそが、アパレル業界の再生を実現していくのではないでしょうか。(ライター:深地雅也)
日本の国産デニムの産地と言えば
ネット担当コトです。先日、「国産ジーンズの産地」についてお話をいたしましたが、「国産デニムの産地」はどうでしょう。そ・の・ま・え・に、「デニム」と「ジーンズ」の違いはOKですか?デニムは生地。 ジーンズは製品。でしたね。でも、普通にジーンズのことデニムって言いますよね。 どっちでもいいんですけど、一応正しいこと知っておいた方がいいかなと思いまして。併せて読みたい記事*「デニムの定義と類似生地」*「デニム」はフランス生まれ?「ジーンズ」はイタリア生まれ?国産デニム・ジーンズの一大産地は、「三備(さんび)地区」です。 昔の国名が、備前・備中・備後だったので、「三備産地」と呼ばれています。■備前(びぜん):岡山県の南東部(児島など)■備中(びっちゅう):岡山県の西部(井原、倉敷など)■備後(びんご):広島県の東部(福山など)その中でもデニムの一大産地は、備中備後地域です。綿作が盛んで、表を藍で染めた備中の備中小倉と呼ばれる綿織物や、備後では備後絣(びんごかすり/日本三大絣の1つ)が作られていました。 こうした伝統技術が元となり、戦後にデニムの一大生産地となりました。>> 綿作が盛んになった理由と藍染めについては、こちらをご参照ください。さて、ジーンズの製作工程をざっくり分けてみましょう。 「紡績」・・糸を作る 「ロープ染色」・・糸をインディゴ染めする 「織布」・・糸を織って生地を作る 「縫製」・・生地から製品を作る 「加工」・・製品に洗い加工や、ダメージ加工を施す 備中備後地域には、そのうち染色、織布、縫製、洗い加工と、紡績以外のほとんど全ての業種があります。中でも、日本三大デニム紡績の一つである「カイハラ」は、紡績から織布まで全てを自社工場内で一貫生産しているような企業もあります。児島のジーンズも、多くがこの地域で生産されたデニム生地を使って作られています。世界に誇る日本のデニム、素晴らしいですね!・・・さて、カイハラといえば、、、 BMCにもありますよね!カイハラデニムを使用したジーンズが!! サイズに限りがありますが、ジャパンデニムを是非お試しください!!しかもセール価格でお買い得♪
アパレルの在庫問題を解決するのはMDの精度? - 勘性とそろばんのバランス(前編)
「ファッションは感性やセンスが最も重要である。」筆者がファッション教育を受けた時代はそんな風に言われる事も珍しくありませんでした。しかし、業界を取り巻く問題の多くは最終的に数字になります。「売上」「粗利」「営業利益」「在庫金額」etc。重要な数値を挙げればキリがありませんが、ファッション産業も当然の如く「商業」であり、売れなければクリエイティブな活動も継続はできません。感性が重視される業界において、数字をしっかり見れる人はごくわずか。そんな状況に警鐘を鳴らし続けている方がいらっしゃいます。【著者】佐藤正臣(さとうまさふみ) 95年(株)ノーリーズにアルバイトとして物流倉庫からスタートし、店頭勤務7年(レディース)。02年より(株)ノーリーズにおいてメンズ(フレディ&グロスター・ノーリーズメンズ)立上をMDとして担当。10年よりフリーランスとして活動開始。シャツメーカーの新ブランド開発の企画サポート。その他、新規ブランドの立上マーチャンダイジング計画など、様々なフィールドで活躍したのち、14年5月末、株式会社エムズ商品計画を設立。小売り企業へのMDアドバイスや専門学校での講義・また海外での講義等。現在、多方面で活躍中。www.msmd.jp今回の対談は、そんなMDのエキスパートである佐藤マサさんにブリッツワークス代表の青野氏がお話を伺ってきました。Q. お二人の数字に対する取り組みを教えてください。青野:社内のお話をすると、現状は僕しか数字が見れないんです。だから今、社員に数字が見れるよう勉強させてるんです。アパレルって数字に弱い人が本当に多い。だから会社の売上・粗利・販管費などの数字を全て公開するようにしました。そうなると社員もシビアに数字を見出し始めましたね。それまでは全く知ろうとしなかったので。今では、人件費以外は会社のホワイトボードに全て掲載しています。関係者全員に数字の意識が無いと、会社の悪いところが見つからないですから。もらっている給与に対して、自分はどれだけ成果を出しているのか、または出していないのか。適正な給与なのかどうかを考えてもらいたいんです。何だったらデザインチームにも同様の事を課してます。その結果、誰がどれだけ利益を出しているのか全部わかるから、組織として健全な状態を保ててますよ。実はマサさんの本も読ませたりしてるんですよ。社員が読み終えたら、ちょうどマサさんに講義してほしいと思ってたんです。会社が拡大すると部下もどんどん増えてくるでしょうけど、そうなると部下に定量的な指示ができないといけないでしょ。将来的にそういう上司になってほしいんですよね。そこで気になったんですけど、マサさんはなんでそんなに数字を意識してるんですか?販売からMDに上がって、そして起業するに当たって、どのタイミングで数字を意識し出したんでしょうか?佐藤:実は販売員の時から数字は意識していたんです。数字に興味の無い販売員って多分いないんですけどね。でも8年くらい前まで、つまりノーリーズでMDやってた時は今のような知識はゼロでしたね。数字の知識無くても売る事って可能なんですよ。お客さんの欲しいものをキャッチできる力があれば。そういう力持ってる人ってアパレルに多いし。自分もそれが出来ていたから天狗になってたんですよ。でも会社辞めたときに何もできない事に気付いたんです。今振り返ってみると、感覚的な部分を重視してたんですが、それだと部下に教える事はできなかったですね。誰にでも言える事だと思いますが、変に成功体験あると、そのプライドが邪魔して学ぶのを怠るんですよ。青野:何がきっかけで数字をちゃんと学ぼうと思ったんですか?佐藤:師匠との出会いですね。アダストリアで勤務していた時に、僕の企画したノーリーズの服を全身着ていた方がいたんですよ。この商品「よく出来てるね」って言ってくれて。で、よくよく話してみると、お前は「感性」でなく「勘性」が優れていると。これは商売勘の事ですね。でも数字に関しては無知すぎると。そこから師匠について学ぶことになったんです。それが地獄の始まりでした(笑)。師匠は教え方が下手すぎだし、パワハラだらけだったんです。今の時代だと一発でアウトですね。自分が何故「わかりやすく教えよう」と思ったかというと、その経験があるから。どんなバカにでもわかるようにって思いながら教えるようにしています。そうなると、自然と部下の成長につながるんです。僕が今の仕事をやるきっかけになったのも、後輩から数字を教えてと言われたからです。「わかりやすいし、これ仕事にした方がいいですよ」って言ってもらえたんですが、その時に、現場の人たちを教育して自発的に動いてもらう事が一番改善につながるって気づいたんですよ。自分は儲からないけどね(笑)「わかりやすく教える」って言葉で言うと簡単に聞こえますけど、数字をわかりやすく言うためにはバカみたいに勉強しないといけなかったんです。余談ですけど、アパレルのコンサルしてる人たちって大体が勉強不足なんですよ。結局やってる事って上から目線でマウンティングしてるだけ。大手で培った手法をあてはめたら業績が上がると思ってるんです。でもそれじゃ誰にもやり方は伝わらないし、売上も伸びませんよね。青野:僕もコンサルの人ってダメなんですよ。そんなに力あるんなら何で自分でやらないのかって思っちゃう。現場で、実務をちゃんとこなしてきた人の言葉でないとスッと入ってこないんですよ。マサさんのお話は現場での経験ありきだから腹落ちしやすいんですよ。佐藤:実務者には好まれますよね。経営者には嫌われるけど(笑)でも、そんなコンサルや上司から、ふわっとした指示が来ると実務者は白けますよね。実務者を白けさせていい会社なんかできませんよ。そういう組織の上層部に限って数字を下に公開しなかったりします。数字なんて隠す意味無いですよ。アルバイトにすら見せた方がいい。その方がみんなやる気が出る。そんな、わかりやすい数字使って実務者のやる気を出さすべきなんです。Q.お二人が商品企画する時ってどうやってますか?佐藤:弱みじゃなくて強みに目を向けますね。例えばノーリーズの時って、自社に物作りのインフラがあったんです。それなのにセレクトに寄っていた。それは勿体無いから前面に出すべきだと思い、自社のアイテムを増やしていったんです。そこから売上・利益が段々伸びていきましたね。僕がやめてからはまたセレクトに戻ったようですけど。青野:マサさんが企画する時って、仕入れに対して粗利や販管費がどの程度になるとか、そういったことを事前に考えていたんでしょうか?佐藤:当時はその考え方は無かったですね。卸の人ってそこまで数字に興味がないから青野さんみたいな意識持ってる人は初めて見ましたよ。卸の人たちには、自分たちの商品が最終的にはどこで無くなってるかを意識しないと終わるよっていつも言ってます。B to Bで小売店に卸したら終わりじゃない。その商品がどこに並んで、どこで売れていって、場合によっては売れなくてセールになって、という流れを見て検証しないと、次の企画に活かせないから意味が無いんですよ。あと、卸でよくいるのは、「ビームスさんこれオーダーしましたよ」って言う人。本当にバカじゃないかと思う。小売側も同じ事言ったりしますけどね。「UAさんどれオーダーしました?」とか。こういうのって品揃えを考えてないって言っているようなものです。自分の店のどこの棚にどういう位置付けでこういう商品があればバイイングするって考えるのが普通です。ショップコンセプトってそういうことだから。青野:例えば卸側から小売店に「消化率ってどのくらいですか?」って聞いたら、「60%」と答えが帰ってくるとします。それだけ聞いたら「優秀な店舗だな」って思うんですけど、SCに出店してたらそれプロパーで売れてないよねっていつも思うんです。それって意味のある指標なのかと。佐藤:僕はこれ以前からずっと言ってるんだけどプロパー消化率って必要ないって思ってます。仰る通り、消化率って切り取り方で大きく変わりますよね。だからごまかせないルールにしないと、いくらでもごまかしが効いてしまう。メディアでもよく意味のない指標が報じられてますけど、それも全部ごまかせないルールにしていないから。本当に一番いいのは現場まで足運んでカウントする事ですね。どのアパレルも使い物にならない数字を使ってる場合じゃないですよ。ていうか、こういう事って別に相手に聞かなくてもいいんですよね。現場見て、店頭の動きみて、仮説立てて考えることが重要なんです。それで予測の精度上がりますしね。青野:でも仮説立てれない人って本当に多いですよね。Q. 仮説・検証が商品をアップデートするという事でしょうか?佐藤:商品分析は逆説で考えた方がいいんですよね。例えば、在庫が多いとか少ないとかは見たらわかります。だから、売れてるけど「これ終わるかも?」って考えることが重要なんです。そこに仮説を立てるんです。逆に売れてない商品でも「お客さんめっちゃ見てる」ってなると、「何がいけないんだ?」って、そこから仮説立てます。実はそこに一番ヒントがあります。分析の目的はお客さんの先の行動を読むことです。だから常に逆説で仮説を立て続けることが重要なんですよ。青野:弊社でも商品企画の段階で仮説を立てるんですが、それで利益を出すものばかり作ると、去年と同じ物とか、去年の物の改良版とか、そういうものばかりになるんですよ。売れてるものばかり在庫を積むと、もちろん売上は上がるんですけど、ブランドってそれだけじゃダメだと思うんですよ。今、新商品を企画してるんですけど、これは先のシーズンを見越した布石として作ってるんです。この商品、受注数がすごく少ないんですが、それってつまり現金化できない商品を置いてるって事になります。それでもブランドの先を考えたら、作っておかなければならない。そんな商品ってありませんか?佐藤:アホだなって思うMDやバイヤーは全ての商品を売ろうとするんですよ。商品の中には、実験的に投入している商品もあるし、これがあるから隣の商品が売れるっていう商品もあります。そういう商品って売れなくていいんですよ。青野:それってロスを最初から考慮した上でMDを設計するってことですよね?佐藤:はい、それは数字の知識が無い時からもそうしてましたね。現場行ってたら、必要性を肌で感じるので。青野:そういう商品は意識的に仕入れ減らしてました?佐藤:極端な話、1点でいい物もあります。最悪、誰か社販してくれたらいいなってくらいですよ。青野:現場からくる感覚値ってことですかね。佐藤:それこそ仮説立てて実験してるって感じですよね。青野:生産の際、その商品が売れないのをわかってて作らないといけない時もありますよね。ロット考えると点数積まないといけないから。作っても利益が残らないってわかってるんですけどね。だから、その分を考慮した上で売上をどう作るか考えないといけないんです。佐藤:その通りです。でも、それってその商品がどれだけ売れるかって予測はついてるんですよ。だらか事前にそれを踏まえた上での計画を立てる必要があるんです。余るのわかってるなら、先に捌き方を考える。これを僕は「前始末」って呼んでる。後始末って労力もお金もすっごくかかるんです。でも前始末って大したことないんですよ。初めから余る数量わかってたらどう対応するか簡単なんで。青野:「前始末」…。いい言葉ですね。そうなると世の中の事は全て前始末で変わってきますね。佐藤:前始末できないならブランドなんかやるべきじゃないですよ。昔はやらなくても生き残れたんですけど、今ってそんな時代じゃない。何かを掛け合わせないと生き残れない。それを実行するには決断力や、前始末のようなリスクヘッジが必要。要はマネジメント力ですね。(後編へ続く)
日本の国産ジーンズの産地と言えば
ネット担当コトです。 日本のジーンズの産地と言えば、ジーンズの聖地として有名な岡山県倉敷市の[児島地区]が思い浮かぶのではないでしょうか。 児島は、1960年代に国内で初めてジーンズを生産したことで「国産ジーンズの発祥の地」として広く知られています。 児島地区は、どのようにしてジーンズの聖地となっていったのでしょうか。 明治時代から「繊維の町」として知られていた児島地区。約400年ほど前は瀬戸内海に浮かぶ島でした。児島という地名もその名残なのだそうです。 戦国時代から始まった干拓によって本州と陸続きになり、度重なる干拓によって更に陸地が広がって平野ができていきました。 でも、海から干拓された土地は塩分が多く米作りには適しません。そこで塩分に強い綿花の栽培が始まり、次第に綿花栽培は広がって優良な綿が生産されるようになっていきました。綿花栽培が盛んになるとそれに伴い、糸作り(紡績)、織布、縫製へと繋がっていき繊維産業が発展。 ミシン業者やボタン製造業者、「染め」に使われる藍作りも始まりました。 そして1965(昭和40)年に、児島の技術を生かした国内初のジーンズを販売。 https://www.bmc-tokyo.com/blogs/journal/journal-21 「国産ジーンズの発祥の地」となりました。 米作りが出来ない・・・→綿花を作ろう!→綿が作れたから布つくろう!→布作ったから縫って製品にしよう!→織物を藍染めしよう!→ジーンズ作ってみよう!お見事!成功の裏には、昔の人の苦労が垣間見えますね。 更に今、児島のジーンズメーカーなどが一丸となりPRしている「児島ジーンズストリート」は、街のあらゆるものがデニム仕様になっていて、インスタ映えする!と人気のようです。[晴れの国]岡山の空にピッタリですね。 児島といえば、地元のナイスコーポレーションさんが製作を請け負っているクラウドファンディングのチノパンもサンプルが完成しています! お待ちの皆様、お届けまでもう少々お待ちくださいね!! そして、こちらはWEBでも少量販売予定です。こうご期待ください!!
日本のジーンズの歴史-その3-
ネット担当コトです。 さて、今回は先週の「ジーンズはどのように日本で根付いていったのでしょうか。」 の第三弾です。 日本のジーンズの歴史-その1- https://www.bmc-tokyo.com/blogs/journal/journal-68 日本のジーンズの歴史-その2- https://www.bmc-tokyo.com/blogs/journal/journal-69 1990年代後半はアメカジブーム、古着ブームが起こり、ヴィンテージジーンズが高値で取引されるようになりました。また、新しいジーンズをあえてビンテージ風にするといった加工技術も発展しました。 爆発的な人気で「エアマックス狩り」という物騒な事件まで起きた「ナイキ エアマックス」やマイケルジョーダンとのコラボモデル「エア・ジョーダン」などのスニーカーブームも、ジーンズ人口を底上げする一因になったことでしょう。 2000年代は、ブーツカットやローライズが、脚を長くスタイル良く見えるということで、女性に大ブレイク。股上が異様に浅い超ローライズなんかオヘソが見えてましたしね。 さらに、ジーンズを刺繍や光もので装飾するなどのデザインも。 2000年代後期はタイトなジーンズが人気に。 この頃「MADE IN JAPAN」のジーンズ品質が、世界で注目されるようになりました。 その一方、2010年以降はGUの980円ジーンズなどファストファッションブランドの低価格のジーンズが流行し、2011年に国産ジーンズメーカーのボブソンが経営破綻するなど、一部のジーンズメーカーは苦境に立たされました。 2010年代は、何といっても進化した機能性でしょう。冬には裏起毛などの保温性、夏には涼しい接触冷感、伸縮性のあるストレッチ機能など、どんどん新しいものが手軽に購入できるように。 デザインやシルエットも多様化し、幅もスキニーからワイド、丈もフルだけでなく、アンクル、クロップなど様々な製品が流通しています。 90年代初頭のようなハイライズが復活していますし、前回で取り上げたようにケミカルウォッシュも復活しています。 「流行は繰り返す」 って言いますから、次は何がリバイバルしますかね! 終わり これも機能的!スマホポケット付きの涼しいイージーパンツ「ラッシュ イージー」
「本物の仕事」こそがファッションの未来を作る
製造・販売・広報・EC…。 一口にファッション業界と言えどもその領域は様々で、一つ畑が違えば全く見知らぬ世界が広がります。 他業界から見ると一様に同じ世界に見えるファッションという領域。同業界の成功者はまるで全能のように見えがちになります。 しかしファッションECの覇者であるZOZOTOWNですら、製造に手を出した瞬間に足元をすくわれる。それくらい、領域が異なる事で実績をあげるのは難しい。今回は「製造・企画」と「販売」という全く違う領域で実績をあげ続け、それぞれ”本物”の仕事を追求するお二人にフォーカスした対談をお届け致します。 四元亮平(よつもと りょうへい) PLAY inc代表。元ポールスミストップセラー。現在はセールスコンサルタントがメイン事業。BMW japan Motorradアパレル部門の専属コンサル、Lee Japanの直営店舗セールスコンサルなど大手ブランドのセールス部門のコンサルティング業務に従事。ファッション販売員の為の情報メディア「 Topseller.style 」主宰。 Q.お二人はどこで知り合われたんですか? 青野:StylePicksの深地さんに言われてTwitterを初めたんですが、知らない人たちと会うきっかけになりましたね。それがあって四元さんを知ることにもなりました。 四元:僕もそれでTwitterで青野さんを認識しました。「この人やばいな」と思ったのは、急に資金繰りのことを発言した時ですね(笑)これ言って大丈夫?みたいな。自分も独立当初メーカー業をしてた時期あるからリアルな感じが伝わってきましたね。この人、相当な修羅場くぐり抜けてるなぁと。 最近よく思うんですけど、賢いビジネスってリスクヘッジしてるじゃないですか。在庫持たず、人を持たずみたいなね。自分自身が今そうだったりするんですよ。今ってそういう働き方がトレンドになってるけど、そういう生き方に対して自分自身がちょっと納得していないところもあるし、ちょっと嫌だったんです。そんな時代に一から在庫リスクちゃんと持って、しかも「定番アイテムであるデニムで勝負してるんだ!」という点が本物の事業展開って感じたんです。これこそ本物の事業家だと。 僕自身が物を作っていた時期に、「物だけ作ってるのはダメ」だと思ってたんです。だから今度は、それだけリスク背負って魂込めてる人たちのために何ができるかって考えたから今の仕事をしてるんですよ。 青野:僕は四元さんのお話を深地さんから聞いていて、最初は「この人何やってる人なんだろう」って疑問だったんですTopseller.styleはライターの南充浩さんがきっかけで知ったんですが、そこで四元さんのブログによく目を通すようになりました。 四元さんの独特の語り口調と、あえて答えを言わない余白のあるツイートを見てると「この人めっちゃ賢い」って印象でしたね。答えをフォロワーに考えさせるスタイルなんだと。それと同時にオラオラ感を非常に感じて「この人怖いんだろうな」とずっと思ってました(笑)ちなみにうちの社員も同じ印象持ってます(笑) 四元:「怖い」っていうのは青野さんには言われたくないですね(笑) Q. その後、直接会おうとなったのはどうしてですか? 四元:会うべき人って、然るべき時に偶然会うことになるって信じてるんです。でも偶然会う為の確率は高めてはいるんですけどね。「偶然を狙ってる」みたいな(笑)そういうタイミングで出会った人って大事にしてるんです。 青野:僕もご縁は大事にしてるんですよ。周りの方々と既に繋がりのある四元さんにもその縁を感じたので、そんな時はどんなことがあっても会うタイミングを作ろうと思いますね。でも初めてお会いした時から、初めてのような気がしないんです。全然違う領域にいるのに考えてる事が結構似ていて。 四元:初めてお会いする人と対峙する時、その人の本質はなんなのかって考えるのが癖なんです。販売現場でもそうなんですが、初対面なのに10年来の友人のような感覚を出せるか。喋り出して3秒くらいで、もうその印象は決まったりします。だからこそ「この人、なんで自分に時間を使ってくれてるんだろう」って無意識に考えていますね。お客さんって自分のことを知ってる人に商品を薦められる方が買いたくなるでしょ?笑 青野:販売員さんってそういう人多いんですか? 四元:はい、職業病ですね(笑) Q.お互いを見て「ここがすごい!」と思うポイントは何でしょうか? 四元:0を1にする人たちに対するリスペクトはずっと持っていますよ。自分はそこが苦手だと思ったから離れましたし。離れてみて気づいたのが、自分は1を10にすることが得意って事。僕は今の力をそういった人たちの為に使いたいんです。特に青野さんのような豪腕社長のサポートはやりがいがありそうです。 青野:四元さんっていつも本当に様々なことを考えてますよね。常に考えてるからこそ、お話される内容が整理されている。そうやって言語化してくれた事を聞くからいつも納得させられる。ロジカルな考えと、販売員さんならではの言語化能力が融合したところが強みだと感じます。これって意識的にやってるんですか? 四元:ブログやりだしたのが原因ですね。書く前にしっかりネタを考えるし、文字に起こすから頭が整理されます。販売員の仕事は、その場その場での言葉の瞬発力が必要なんですよね。特に販売スキルは理論として説明できるようになると再現性も高くなる。販売員ってアスリートと同じだと思ってますよ(笑) Q.お互いの領域について思う事ってありますか? 四元:ブランドやもの作りに対する熱量を感じています。悪い意味ではないんですが、販売をする人間にとっては「どんな物であろうとお客さんに喜んでもらえる」って思ってやってます。ただ、1点重要なのは0から1の部分。つまりブランドの「コンセプト」や「ストーリー」はすごく大事なんです。もちろんデザインの良し悪しも関係無くないんですが、僕自身が商品と会話できる物でないと売りたくないんです。あぁこのブランド勝ちに来てるなって感じると売りたくなる。BMCはそれを感じるんですよね。 青野:本質的にはやってる事は同じなんだなぁって印象です。ブランド側は逆に「誰でも売れるもの作り」を考えますね。サラリーマン時代は、企画部門って自分の会社の営業にプレゼンするだけだったんですけど、BMCを始めて飛び込み営業を散々やりました。その時に小売店が必要としている事は何か?解決・提案を繰り返してるうちに、「この人が何を求めてるのかがわかれば何でも売れる。」と思うようになりました。to Bとto Cのセールスの違いはあるにせよ、人に伝える熱量やそれを買った人がどうなるか?という事は考えますし、そのあたりが似てるのかなって。 ただto Cと違う点は、Webのおかげである程度ユーザーのニーズを定量的に測ることができるようになりましたけど、まだまだ「予想」が占める部分は大きいですね。 四元:もの作りの人たちはそういった要素が必要だと思いますよ。トレンドって予測不可能ですから。お話聞いていると、作る人は「何が売れるんだろう?」と考えるけど、僕たちは「顧客はなんで買うんだろう?」って考えるから、それでうまく双方が成立しているんですね。双方が歩み寄って考える事が大事なんだなと。 Q.お二人にとってファッションとは何でしょうか? 四元:単純に服を好きになってからは幸せですよ。生まれてから死ぬまでファッションは必要だし、そこに関われてるのが楽しい。だから服の仕事をしているのかもしれませんね。 青野:僕もファッションは大好きなんです。こんな怖く見られる僕でも、ファッション次第で品良く見せてくれたりしますから(笑)絶対誰にも侵されない感性的な領域ですよね。でも、創業からずっと思っている事があって…。それは”正解がどうかわからないものを売っている。根拠の無いもので勝負している。”というところです。だからこそ、「ファッションって何なの?」とずっと思っているんです。そういった部分がコンプレックスにも感じています。 四元:それはわかりますよ。ファッションってキレイゴトで紡がないといけない世界なんですよ。でも一方で「製造」に関わるとそうも言ってられない場合がある。売れないと収入が得られないし、生産ロットの問題だってある。キレイゴトだけではやり切れない部分なんていくらでもありますから。 青野:そうなんです。SNSでキレイゴトばかり言っている製造関係の方々を見ると「本気で言ってるの?」と思ってしまう。それくらいリアルはもっとドロドロしていますし、ファッションを商売のツールにした瞬間からキレイゴトだけでは生きていけなくなります。 四元:その代わりに販売員がいるんですよ。キレイゴトってちょっとでも躊躇ったらダメです。だから自分たちが代わりに全力でキレイゴトをお客さんに言っているんです。青野さんのようにそれを影で支えてくれて、そのキレイゴトを実現してくれる人がいるからこそ出来る事です。 どれだけ真剣に心の底から恥ずかしがらずキレイゴトを言えるか、それができる販売員が勝つんです。お客さんもそれがキレイゴトってわかっているんですよ。そこにどれだけ夢を見させてくれるかを求めてるんです。そこに商売っ気が見えた瞬間に終わる。もしかしたら作る側もついてきてくれないかもしれません。だから販売員がキレイゴトの翻訳家にならないといけないんです。それを覚悟持ってやるのがセールスなんですよ。 青野:確かに同じキレイゴトを言っている人間でも中身があるかどうかは行間を読めばわかりますからね。言っている事が「何かの本を読んだ?」とか「誰かが言ってた事の受け売り?」って思ってしまう。薄っぺらいんですよ。きっと覚悟の違いなんでしょうね。 四元:僕が近くにいたいって思う人は、「この人の未来が見たい」「未来に期待したい」人なんです。ファッションを通してお客さんにもブランドにも素晴らしい未来を見てほしいし、それを自分自身がサポートできるならこんなに幸せな仕事は他にありませんね。 同じ年に生まれたお二人ではありますが、これまで全く違う領域で生きてきたのに共通する要素が非常に多い事に驚きました。 インタビューしている側からすると、お互いの追求する「本物」という価値観が共通言語を生み出している…、そんな印象を受けました。 ファッション業界はメディアで報じられているような「通説」とされている事が間違っているケースがよく見受けられます。これも対談中にお話されていた「キレイゴトで紡がれる世界」ならではなのかと思いますが、片やキレイゴトを貫いているもう一方でそろばんを弾くといったお二人が表裏一体になっているからこそ成り立つのだと、真の実務家を見てそんな事を考えさせられました。 この二人の描くファッションの未来がどうなっていくのか、今後も注目していきたいと思います。(ライター:深地雅也)