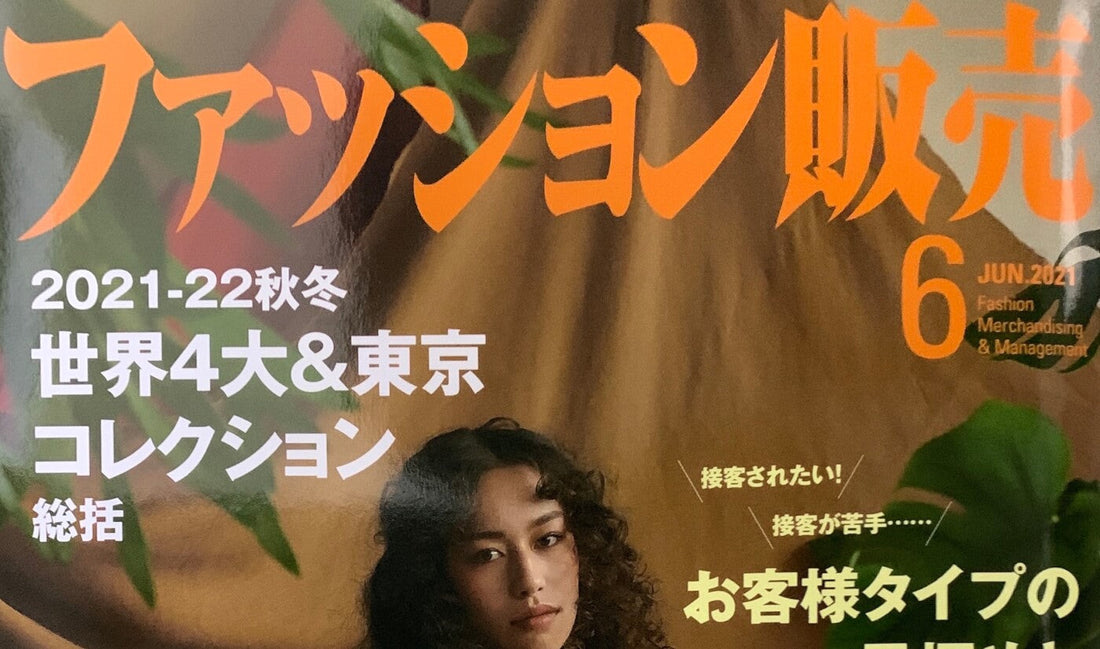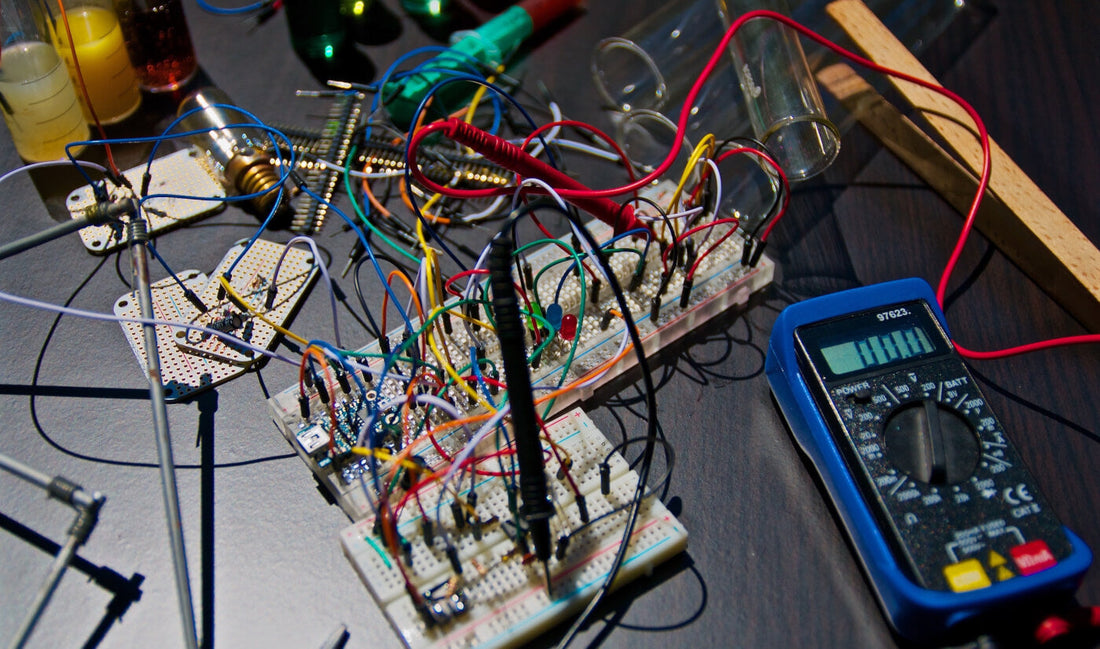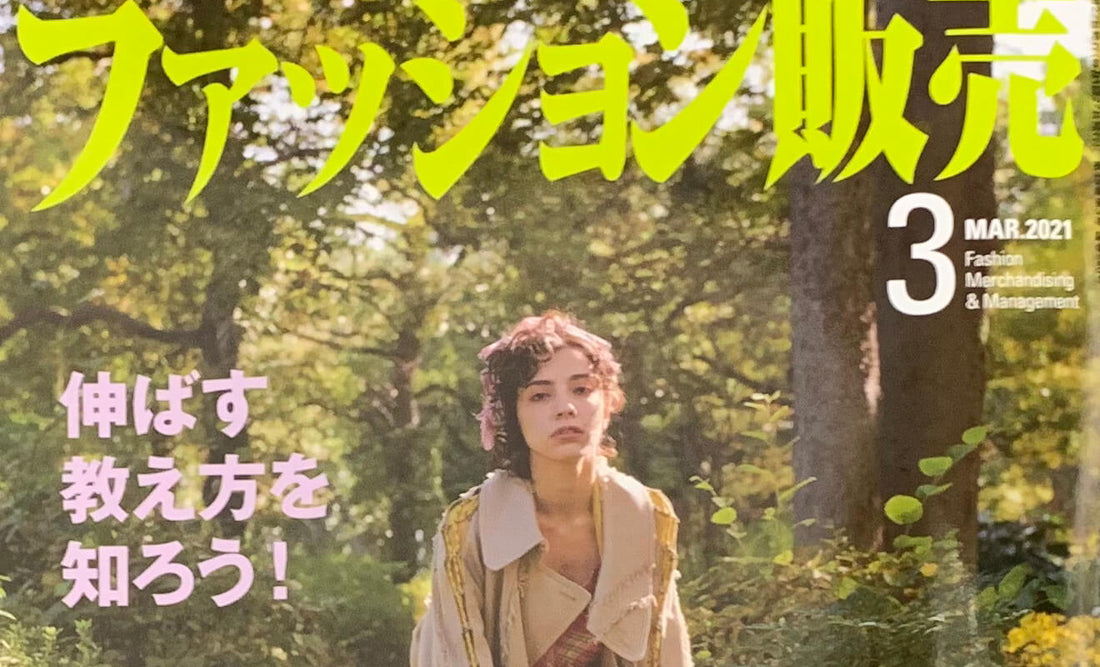Journal
南充浩オフィシャルブログ:衣料品ブランドの発信もYouTubeの時代
アパレル業界で著名なライター南充浩さんのブログにBMCの活動が取り上げられました。BMCデニムデザイナー青野(ローリー青野)のYouTube活用の一部が南さんの記事に取り上げられています。 (南充浩オフィシャルブログ:衣料品ブランドの発信もYouTubeの時代) =転載=ちょうど1年前の今頃のことである。 詳しい説明は専門の方にお任せするとして、平たくいうとGoogleの検索のアルゴリズムが大きく変更され、ブログより動画の方が上位に表示されやすくなった。 そのため、このブログも昨年5月から大きく訪問者数、PV数が減り、今はそのまま落ち着いて推移して・・・・・(続きはコチラ) https://minamimitsuhiro.info/archives/7680.html FASHION × BIKE YouTubeチャンネル【 ローリー青野の 10 MILES BIKE LIFE 】
MSMD:超入門!ブランドのビジネス計画と経費計画の話。
MDプロフェッショナルMSMD マサ佐藤さんのホームページ ブログに不定期にて記事を寄稿させて頂いています。 BMC視点ではないデニムデザイナー青野の考え方がよく分かりますよ。ご興味ある方は、是非お読み下さいませ。 https://msmd.jp/archives/6477 アパレル業界・それ以外の業界の皆様、MDの考え方はとても大切です! FASHION × BIKE YouTubeチャンネル【 ローリー青野の 10 MILES BIKE LIFE 】
(寄稿)ファッション販売6月号:夏のデニム特集記事
ファッション販売 6月号 素材・生地の知識 夏編のデニム特集の記事をBLITZ WORKS青野として書かせて頂きました。 ねっ? デニムの記事を書かせて頂くほど・・・知識と経験がございます(笑) BLUE MONSTER CLOTHINGでジーンズメーカー!ジーンズブランド!って言ってますが、これで信用して頂けましたでしょうか(笑)???知識と経験に裏打ちされた企画開発を続けています!!! DENIM × FASHION × FUNCTION がBMCのコンセプトです!!!デニム特集が気になる方は・・・ ファッション販売3月号をお買い求め下さいませ。FASHION × BIKE YouTubeチャンネル 【 ローリー青野の 10 MILES BIKE LIFE 】
MSMD:【初めてのブランド】はアイテムを絞る事が重要!
MDプロフェッショナルMSMD マサ佐藤さんのホームページ ブログに不定期にて記事を寄稿させて頂いています。 BMC視点ではないデニムデザイナー青野の考え方がよく分かりますよ。ご興味ある方は、是非お読み下さいませ。 https://msmd.jp/archives/6266 アパレル業界・それ以外の業界の皆様、MDの考え方はとても大切です! FASHION × BIKE YouTubeチャンネル【 ローリー青野の 10 MILES BIKE LIFE 】
『接触冷感』はなぜ触れると涼しく感じるのか
ネット担当コトです。BMCでも採用されております"着るとひんやり涼しく感じる『接触冷感』と言われる高機能素材"ですが、どうして着ると涼しく感じるのか?今日はここのところを掘り下げてみます。==========================優れた「接触冷感」生地が日本で開発された背景 ==========================夏の電力不足に向け、政府が呼びかけている「節電アクション」。 その中でも、節電しながら快適に過ごすための工夫を推し進めているのが 2005年に提唱された「クールビズ」です。画像参照元:環境省 クールビズ夏になると、霞が関の職員がアロハシャツや「かりゆし」で仕事をするニュースも風物詩ですね。政府のサポートもあり、世界に先駆けて高機能繊維の開発に取り組んでいた日本の繊維製品メーカーは、「高機能繊維」の一つである「接触冷感」の開発に勢いを伸ばし、注目されていくわけです。======================そもそも、なぜ「接触冷感」は涼しく感じるのか。 ======================触ったときに心地よいヒンヤリ感のある、まさに「接触」した時に「冷感」を有する素材です。どんな仕組みかといえば、・繊維中に水分を多く含むこと ・熱伝導率が高いこと、 ・さらに触った時に少し硬く感じる(シャリ感)などが接触冷感性能に影響しています。水分を多く含むということは、親水性のため素早く汗を吸収し、 液体が気体になる時に周囲の熱を奪う作用が働くため、 暑い日でも生地の内部を快適に保つことができるのです。熱伝導が高いということは、熱を逃がしやすいというメカニズムです。 熱拡散率が高く、素早く熱移動するため(熱が瞬間的に多く移動する)、 生地内の水分を素早く吸収・拡散して気化熱を奪うことと 素早く熱移動させることの2つの働きで冷感効果をもたらします。繊維の中に水分を多く含むため、硬くてシャリ感があり、 触れたところが涼しく感じます。シャリ感のある天然繊維の麻(リネンなど)は、 古代から接触冷感のある素材として知られています。 夏服の製品によく使われていますよね。======================チームでなしえた「接触冷感」技術。 ======================続々と開発される「接触冷感」の技術。これらの素材を活かしたものづくりを行うには、 優れた加工技術(織編加工、染色加工)が欠かせません。先端の素材技術と、それを加工する技術がそろって、 新しい高機能繊維製品が生み出されていくのでした。この夏は、Wearable Coolを着て 涼しげな顔で快適な日々を過ごしましょう!参照元:経済産業省 http://www.meti.go.jp/setsuden/archives/seikatsu/2011/docs/coolbiztech/meti_j.pdf注意点としては…接触冷感での注意点なのですが、実際に「涼しくなる」「冷たくなる」わけでは無いという事ですね。生地そのものが「冷たく」なるわけではありませんし、また着用していたら体温がどんどん下がるとかそんな効果もありません。着た瞬間に「ヒヤっ」とするというのが接触冷感の効果です。生地が肌に触れた「瞬間」に「冷たく感じる」というのが、読んで字のごとく「接触冷感」の意味です。衣類がずっと冷たいとか衣類そのものの温度が下がるとかそういう機能ではありません。あくまでも皮膚と生地が接触した時に冷たく感じるという機能になります。そして、着用していると体温ですぐに温まります。接触冷感機能はそれほど持続力があるわけではないのです。ここも重要ですので覚えておいてほしいところです。「接触冷感」は生地の組織によっても実現できますが、薬剤などの加工によっても実現可能です。接触冷感用に用いられる薬剤としては、キシリトールが有名です。キシリトールというと、虫歯を防止する甘味料として有名でガムなどに用いられることが多いのですが、キシリトールを生地の表面に加工すると、接触冷感効果があります。キシリトールの粉末は水に溶ける際、水の温度を下げる機能があります。これを利用したのがキシリトール加工の接触冷感衣料品なのです。ただし、キシリトール配合のガムや歯磨き粉をいくら生地に塗っても効果はありませんのでご注意ください。またトレハロースという甘味料もキシリトールと同様の機能があります。ですから、キシリトール加工、トレハロース加工というのがあれば、それは「接触冷感」機能があるという証となります。今年の夏に「接触冷感」衣料品を買う際は加工にも注目してみてはどうでしょうか?
セルビッチとは
一般的に「赤耳(RED TAB)」と呼ばれるセルビッチ。高負荷化価値なデニム生地の象徴とされていまして、デニムマニアの中には、セルビッチデニムファンの方も多いかと思います。 ちなみに、以前販売したBMCの国産リジッドジーンズも、セルビッチでしたね。 BMC 国産セルビッチジーンズ R78HV 人気を博したリーバイス501が糸色に赤を使用したため、セルビッチといえば「赤耳(アカミミ)」と認識されるようになりました。 ※耳自体はデニム生地に限らず、すべての生地に存在しています。 セルビッジジーンズの裾を折り返すと、上の画像のようになっています。ロールアップで穿くとチラリと見えておしゃれ。 -------------------------------セルビッチデニムとは------------------------------- セルビッチデニムとは、旧式織機でシャトルを通して、カタカタと織られたデニム生地で、生地の両端に「耳」という部分ができ「ほつれ止め」が施されています。 シャトル(杼/ひ)とは、織物を織るときに、経糸の間に緯糸を通すのに使われる道具です。ぴんと張った経糸の間に、緯糸を収めたシャトルを左右の端から反対側の端まで通して織り上げていきます。 出典:ウィキメディア・コモンズ (Wikimedia Commons) シャトル織機は基本手織りと同じ方法で織られるため、手織りに近い素材感があります。 対して、最新の織機はコンピュータ制御のためシャトル織機とはケタ違いの生産効率があります。「革新織機」と呼ばれています。 ---------------------------------------------------------セルビッチデニムのメリット・デメリット--------------------------------------------------------- 旧式の織機を使用して生産されるセルビッチデニムは、一般のデニム生地の数倍織るのに時間がかかります。 そして、通常のデニム生地の横巾が150cmなのですが、旧織機を使ったセルビッチデニムは横巾80cm程度しか織れません。 セルビッチはデニム生地の耳を使う、パターン・裁断も重要です。 裁断の略図を見ると、巾が狭いセルビッジ生地の場合、1本のジーンズを作るにもたくさんの生地が必要になります。生地原価もあがり、製品も高価になります。 また、セルビッチの生地は厚手が多く縫いにくく扱いづらいので、きれいに織り上げるには職人技が必要です。 今では革新織機の登場により、シャトル織機は減少してあまり残っていないそうです。機械のメンテナンスも大変だと聞きました。 つまり、旧型織り機で織られたデニムは希少価値があるということです。 また味わいという点でもマニアにはたまらないポイントですよね。 ❝ 革新織機は高速回転で生産するため、準備工程で糸に付ける糊の量が多く、製織時にかける糸の張力が強い。そのため織り上げた生地の表面は均一できれいだが、平板な感じになってしまう。逆にシャトル織機だと、糊の量が少なく糸の張力も弱いため糸の屈曲が深くなり、凹凸感のある織物になる。これがセルビッジデニムならではの味わいだ。出典:繊研新聞 ❞ ---------------------------------------------------------セルビッチデニムの大切な工程「延反」--------------------------------------------------------- 生地は輸送の際、筒状に巻かれたり折り畳まれて袋詰めにされたりして、生地そのものの重みや摩擦、糸の引っ張りなどによる負荷を受けます。 それを裁断前に広げ、生地をリラックスさせて元の状態にもどし、一気に裁断できるように整える【放反】【延反】という工程があります。 セルビッチデニム生地は耳を残した裁断が必要です。そこで編み出されたのが、セルビッチデニムだけにある延反技術【耳揃え】。 裁断台にデニム生地を延ばして、幾重にも重ねていきます。 これを行わないと、ジーンズの両脇にセルビッチ(デニムの耳)が出てきません。 ジーンズを製造する上であまり注目されない工程の「延反」ですが、セルビッチデニムを使用したジーンズを製造する上でとても大切な工程なんです。 ---------------------------------------------------------デニムは綾織、でも耳部分は朱子織--------------------------------------------------------- デニムは綾織、でも耳部分は朱子織です。 綾織と朱子織については、こちらのジャーナルで説明していますのでご参照ください。 【織り】なのか?【編み】なのか? https://www.bmc-tokyo.com/blogs/journal/journal-23 ---------------------------------------------------------何故、赤耳が重視されるのか?--------------------------------------------------------- デニムに限らずすべての生地の両端に耳が存在するのは、生地が端からほつれてこないようにするためです。 しかし、デニム生地の耳、とりわけ赤耳が重要視されるようになったのは、95年ごろから盛り上がったビンテージジーンズブームに端を発しています。 この赤耳は1970年ごろまでのデニム生地には付けられていたのですが、徐々に減っていき、技術革新が進んだ80年代にはほぼ姿を消していました。 ところが「古き良き時代のジーンズ」への価値が高まったビンテージジーンズブームが起きたために、当時のデニム生地には付けられていた赤耳も注目を集めることとなったのです。 極端な言い方をすれば、赤耳付きは正統派ビンテージ、赤耳無しは80年代以降であまり価値が高くない、そういう価値観が形成されていきました。 ビンテージジーンズブームでは何十年前の古い商品が高値で取引されましたが、そのような物の数には限りがありますから、マス層には行き渡りません。当然、当時の商品をコピーした「レプリカ商品」が多数生み出されることとなり、ビンテージジーンズブームの本体を支えたのはこのレプリカ商品だったと言っても過言ではありません。 商品のデザインをレプリカするなら、当然生地もレプリカするということになり、ここでレプリカの赤耳デニム生地が多数生み出されることとなりました。 そうです。わざわざセルビッチ付きデニム生地をレプリカして作るようになったのです。 先述しましたように、昔の織機はシャトル織機と呼ばれるものでした。これが80年代に技術革新が進むと、姿を消していったのです。もっと高速でもっとたくさん織れる織機が次々と登場し、デニム生地工場の織機もそちらに置き換えられていったのです。 ちなみにこの「シャトル」というものが、スペースシャトルの語源になっているのです。地上と宇宙をシャトルのように往復することからスペースシャトルと名付けられました。 それからもう一つ、その辺りから大きく変わったのは、生地の幅がほぼ倍増して広くなったのです。ビンテージデニム生地のころの織機の幅はだいたい70~80センチしかありませんでした。この両端がセルビッジです。ですが、第二次世界大戦以降の技術革新によってより効率的により大量に生地が織れるように、織機の幅は倍増します。狭くても1メートルを超えるようになり、平均すると120センチ~150センチ程度の生地幅になりました。 70~80センチの生地幅を小幅・狭幅と呼び、1メートルを越える新型織機の生地幅を広幅と呼びます。 ビンテージジーンズブームが起き始めた95年には実はデニム生地工場のほとんどは広幅織機に代わっていたのです。 ではどうやってセルビッチデニム生地を復活させたのかというと、昔の小幅織機を探し出して設置したのは言うまでもありません。幸いなことに古い文物を保管しておくことでは世界から定評がある我が国には使われていない小幅織機が大量に残されていたのです。 ですが、95年以降の生地流通量と残されていた織機の台数から考えると、すべてがこれで賄われたとは考えにくく、広幅で両端だけでなく、生地の中央にセルビッチ柄を入れて織るという「広幅の疑似セルビッチデニム生地」が多数生産されたと言われています。実際にデニム生地工場からも聞いたことがあります。 レプリカジーンズにはこの疑似セルビッチ生地が多く使われていたようです。 正直なお話、現代に復活したセルビッチデニム生地と通常の広幅デニム生地の一体何が違うのかというのは、穿き比べてみてもよくわかりません。格別に気持ちいいわけでもないですし、格別な機能性があるわけではありません。「付いている」というところに満足感を覚える程度ではないでしょうか。 特に耐久性が上がるわけでもありませんし、昔ながらっぽさがあるということぐらいではないかと思います。 ---------------------------------------------------------いろんな耳の色--------------------------------------------------------- セルビッチデニムは赤糸を使った「赤耳」が主流ですが、青糸の「青耳」、黄色糸の「黄耳」、「紫耳」、ピンク色の「桃耳」なんかも出てきてバリエーションが豊富になりました。 実は色ごとに納付するブランドを示していたという説があります。有名な「赤耳」は当時「リーバイスに納品するデニム生地」という意味だったそうです。青なら〇〇ブランド、黄色なら〇〇ブランドという風に、出荷するときに送り先を間違えないように色を分けていたということなのだそうです。 ですから、赤耳付きのリーバイス以外のブランド品というのは、本来の意味からは少しずれるのかもしれませんね。
MSMD:【YouTube】を使ってブランドを立ち上げる実験
MDプロフェッショナルMSMD マサ佐藤さんのホームページ ブログに不定期にて記事を寄稿させて頂いています。 BMC視点ではないデニムデザイナー青野の考え方がよく分かりますよ。ご興味ある方は、是非お読み下さいませ。 https://msmd.jp/archives/6019 アパレル業界・それ以外の業界の皆様、MDの考え方はとても大切です! FASHION × BIKE YouTubeチャンネル【 ローリー青野の 10 MILES BIKE LIFE 】
藍染めとインディゴの違い
「ジーンズは何故インディゴなのか?」の続き、 ジーンズは何故インディゴなのか? 日本古来からあるブルーカラー「藍染め」との違いについてです。 ----------------------藍染めについて---------------------- 人類最古の染料ともいわれている「藍」。 紀元前より世界各地で青色の染料として利用され、ツタンカーメンのミイラの衣装にも藍染めが使用されていたそうです。 藍染めが日本に伝来したのは奈良時代ごろ。 藍の葉は昔から薬効が広く知られ、薬用植物として解熱、解毒や抗炎症薬等など、貴重な民間薬として使用されていました。 濃く藍染した布は耐久性が増し、抗菌性・消臭性にも優れ、害虫・蛇避け効果があるため作業着や足袋などに、 また、燃えにくく保温性にも優れているとされ、道中着や火消しの半纏にも多く用いられました。 引用:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 日本で使う「藍」はタデ科の植物ですが、「藍染め」は植物に含まれるインディゴという成分を使って染める製法のことなので、タデ科以外にも各国によってインディゴ成分を含む植物が藍染めに利用されています。 日本ではタデ科の「蓼藍」、インドの「インドアイ」(マメ科/木藍-もくらん-)」、琉球では在来の「琉球藍」(キツネノマゴ科)、ヨーロッパ「ウォード」(アブラナ科)、北海道「タイセイ(エゾアイ)」(アブラナ科)などなど。同じインディゴ成分を含む藍染めといっても、使っている植物が異なるために色合いが違っています。 -------------------------------------------藍染めとインディゴ染めの違い------------------------------------------- 藍染めと合成インディゴの染め上がりは、同じ染め方をすれば見た目にはあまり違いがわかりません。 藍染めは染料液(すくも)というを発酵させた液体を使用した天然染料に対し、 藍染め用のすくもと藍甕 化学薬品を使用して染めた合成染料がインディゴ染めです。 引用:カイハラ株式会社 染めの原料としての違いは、 藍染めは天然物のため安定した染めが難しく、染織過程の手間もかかり職人の技が必要です。 糸の中まで染めの色が浸透し、時間を経ることにより深みのある色が定着していきます。 また、使い込んで洗濯を繰り返すうちに、色が落ち着き、柔らかく肌に馴染むようになります。 天然ということもあり藍染めのほうがもちろん高価。 工業生産のインディゴは安価で大量生産が可能です。 天然よりも不純物がないため鮮やかに染まり、藍染めと違って着用した時の摩擦や洗濯により色落ちするという欠点ともいえる特性が、ジーンズでは魅力とされています。 ジーンズの生地であるデニムは、ロープ染織という染織方法でインディゴが糸の真ん中まで染まらない方法で染めているのも特徴でしたね。 デニムのロープ染色のってナニ!? ジーンズの染色としてインディゴが主流の今、藍の栽培も縮小し、藍染めはほとんど使われることがなくなりました。 ---------------------------現代に生きる藍染め--------------------------- 日本で藍染めは江戸時代に最盛期を迎えます。 「紺屋」といえば江戸時代の染物屋の代名詞。染め物といえば大半を藍染めが占め、城下町には必ずと言ってよいほど紺屋町があったそうです。 着物、浴衣、野良着、のれん、前掛け、手ぬぐい、足袋、火消し半纏、風呂敷などなど。思いつく藍染め製品はきりがありませんね。江戸の町はまさに藍色の町でした。 現代の日本でも、野球日本代表「サムライジャパン」、サッカー日本代表「SAMURAI BLUE」や、「なでしこジャパン」のユニフォームなどに使用される「青」。青はどうして日本代表カラーになったのでしょうか。 明治時代の初め、来日したイギリス人科学者が、町にあふれる藍染めを見て、藍色を「ジャパンブルー」と記したということに由来しているそうです。 また、サッカー日本代表のユニフォームには藍染の生地で最も濃い色の呼称「勝色(かちいろ)」が使われていました。 日本の伝統色である深く濃い藍色。武将たちが戦いに挑む際身にまとった、鎧下と呼ばれる着物に使われる藍染の生地は【勝色】の深く濃い藍を出すためには布を叩きながら染めるため、「叩く=褐(かつ)=勝つ」にかけて、勝利への験担ぎをしていたと言われている。引用:IGNITE(イグナイト) 最近では、天然染料による染色が見直されて、高価な藍染めのジーンズも人気のようです。 藍染めもインディゴも、どちらも穿きこむ人によってに経年変化が見られそうで面白いですね。 個人的な話になりますが、筆者が毎年着ている祭り衣装の中で、股引とどんぶりは若い頃に町内会のご老人からいただいた年代物の藍染めの逸品。今のと違ってストレッチ機能なんてなくてパッツンパッツンなんですが、木綿の裏地なんかが付いていて藍色も年を経ていい色具合。 もう販売しているところも見かけないし、もしあっても高そうなので大事に着ようと思ってます。 -------------------------------------------藍染・インディゴが普及した理由------------------------------------------- どうして藍染が普及したのかですが、先述しましたように機能的なメリットがあったからです。この藍にはインディゴ成分が含まれています。藍の天然インディゴ成分に対して、合成インディゴを用いたのが現在のデニム生地です。どうして合成インディゴを使用するかというと、藍というのは扱いが非常に難しいのです。 発酵させた「すくも」という染料液の温度管理が難しく、発酵させすぎてもダメになりますし、発酵させなさ過ぎてもダメになります。良い発酵度合を保ち続けるには管理を厳格にしなければならず、このノウハウは一朝一夕で身につくものではありませんでした。 そのため、扱いが比較的容易い合成インディゴが用いられるようになり、今に至っているというわけです。 現在、合成インディゴはロープ染色という方法で染められ、藍染とはやり方がまったく異なりますが、染め上がりは一見するととても似ています。しかし、使い込んでいくと決定的に異なる部分が見えてきます。 インディゴ染めのデニム生地は摩擦によって色落ちし、だんだんと色が薄くなっていきます。またヒゲやアタリと呼ばれるようなメリハリのある色落ちがあります。 一方、藍染ですが、インディゴ染めに比べると色落ちしにくいのが最大の特徴です。また、色落ちしてもインディゴ染めデニムのよりもメリハリのない色落ちをします。いわば均一に色落ちすると言った方が分かりやすいでしょうか。 あとは値段です。藍染は量産しにくくコストが高いため、概して製品は高額になります。インディゴ染めのデニム生地よりもはるかに高額となります。現在では国内の藍染は細々と各地で行われているくらいになってしまいました。 -------------------------------------------藍染とデニムの関係------------------------------------------- 藍染とデニムの関係はまだ続きます。 今では「日本製デニム生地」といえば、世界的にも高い評価を受ける場合が多く、国内生地の中では最も成功したものの一つだといえますが、実は日本でデニム生地が生産されるようになったのは、比較的最近のことなのです。 ジーンズが国内にもたらされたのは第二次大戦終戦後すぐでしたが、国産ジーンズが登場したのは1960年代になってからです。この時、デニム生地はどうしていたのかというとアメリカから輸入していたのです。 そして、国産が始まったのは1970年のこと。 カイハラが国産化に成功したのです。カイハラはもともと、藍染めした糸を使った備後絣を製造していました。カイハラが本社を置く、広島県福山市は藍染の糸を使った備後絣の産地でした。 1960年代まではカイハラは備後絣を製造していたのですが、そこから1970年にロープ染色機を完成させ、デニム生地工場へと転身したというわけです。藍染の備後絣とはいくつか異なる点はあるものの、共通点も多いインディゴ染めのデニム生地へと転身することで生き残ったというわけです。 その後のカイハラの知名度は広く世間に知られている通りです。 デニムのカイハラのルーツは藍染の備後絣にあったのです。
(寄稿)ファッション販売3月号:春のデニム特集記事
ファッション販売 3月号 素材・生地の知識 春編のデニム特集の記事をBLITZ WORKS青野として書かせて頂きました。 ねっ? デニムの記事を書かせて頂くほど・・・知識と経験がございます(笑) BLUE MONSTER CLOTHINGでジーンズメーカー!ジーンズブランド!って言ってますが、これで信用して頂けましたでしょうか(笑)???デニムで製品を作るって、製品商社にお金を払えば誰でもできます。 今のワーク業界のデニム製品なんて、まさにこれですよ・・・ うちがなぜ他社より高いのか? うちがなぜ他社より本格的と言われるのか?その答えが、この記事です。知識と経験に裏打ちされた企画開発を続けています!!! DENIM × FASHION × FUNCTION がBMCのコンセプトです!!!デニム特集が気になる方は・・・ ファッション販売3月号をお買い求め下さいませ。FASHION × BIKE YouTubeチャンネル 【 ローリー青野の 10 MILES BIKE LIFE 】